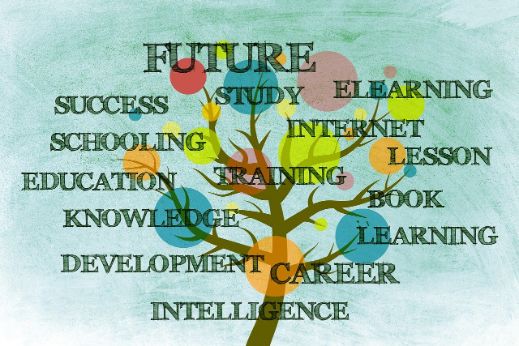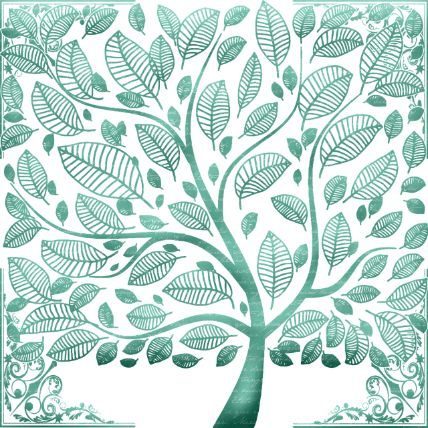親としては、子どもにちゃんと勉強して自分みたいに後悔してほしくない、自分のやりたいことをやれるようになってほしいと考えますよね。
結論、親の言動によって、子どもの勉強する意欲は大きく影響します。
この記事では成績上位の子どもの親の言動や、子どものやる気を引き出す方法を紹介します。
ここでいう子どもは、小学生を指します。
以下のサイトの記事をまとめました。
✔OXFORD LEARNING ⇒ HOW TO KEEP YOUR CHILD MOTIVATED WHEN STUDYING: 11 TIPS FOR PARENTS
こんな親なら子どもは勉強する

子どもが小さいうちは親の言動が子どものやる気に関わってきます。
成績上位の子どもの親は、子どもの学習に興味をもって積極的に関わっています。
具体的に、以下のような親であれば、その子どもは勉強しています。
- 子どもとよく話す
- 新聞を読んでいる
- 博物館や美術館に連れて行ったことがある
- 子どもの成績を知っている(文章力は弱いが読解力はある などの中身まで)
- 子どもの勉強に積極的にかかわる(ほめる、一緒に解決する)
- 「勉強しなさい」といわない
- 小学高学年になれば進学先や将来のことを話し合う
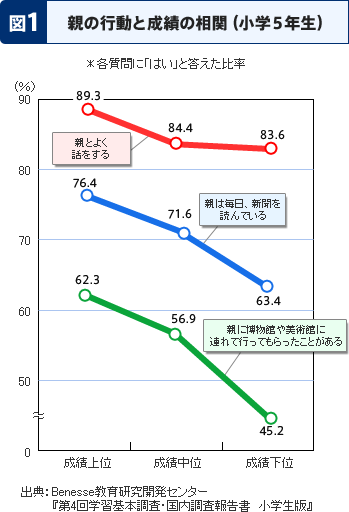
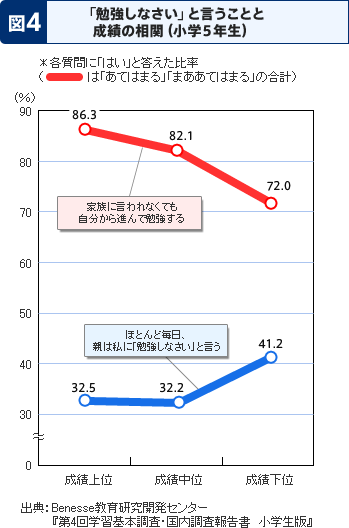
親が社会に関心をもつ姿勢や、教育に対する考え方が重要です。
子は親の背中をみて育つとはよくいいますね。
そして、小言が多いのが問題です。
勉強しなさい!宿題やったの!早くやりなさい!などついついいってしまいます。
そういった小言が子どものやる気をそいでしまいます。
自分から勉強するように仕向けるためには、ほめることが大切です。
自分が子どものとき、親にいわれていやだったことを同じように、自分の子どもにいっていませんか?
子どもをやる気を引き出す11のヒント
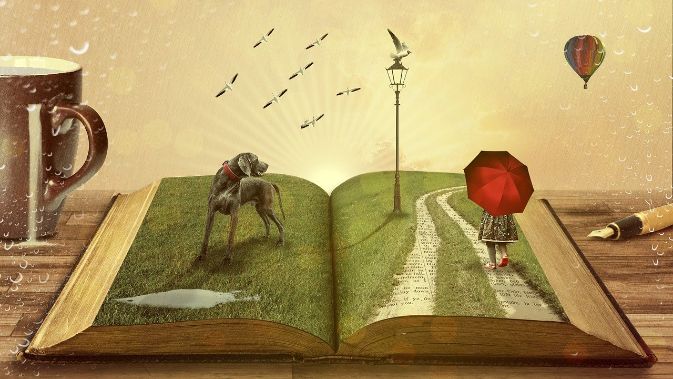
この記事から要点をまとめました。
無理強いさせるのと、自ら進んでやるのとでは大きな違いがあります。
あれダメ、これダメというような、否定しないな方法で習慣づけることが大切です。
無理にさせてしまうと怒らせてしまい、やる気にさせることはずっと難しくなります。
やる気にさせる11のヒントを紹介します。
具体例として我が家のパターンを紹介します。我が家は小学生の息子が二人います。
- やる気が出ない原因を探る
- 環境を整える
- 学習計画をいっしょにつくる
- ごほうびを決める
- ストレス対処
- 成績より行動にフォーカスする
- 小さな目標を立てる
- 別のやり方を試す
- 休憩時間をつくる
- 体を動かす
- 第三者のヘルプ
1. やる気が出ない原因を探る
問題起きる時は原因があります。原因が分かれば対策ができます。
例えばこんなことはありませんか?
- 問題の意味が理解できない
- 勉強の問題が簡単すぎる
- 勉強のやり方が合ってない
- 学校での悩みごとがある
- 自信がない
我が家では、宿題以外の勉強をほぼやっていません。
学力がどの程度がはかることが難しいです。
2. 環境を整える
- 静かで、注意をそらすものがないようにする
- 集中できるように、勉強する前におやつ等をあげておく
- えんぴつなど勉強に使うものはすぐに手に取れるようにしておく
必要なものはすべて準備しておくことで、言い訳をいわせないようにする。
うちはこれができていません。
テレビやYouTubeをつけっぱなしで宿題をしていることがよくあります。
リビング学習ではある程度うるさいのはしょうがないです。
漢字の書き取りをするときだけは、YouTube見ながらでもOKにしています。
3. 学習計画をいっしょにつくる

机に向かう時間を習慣づけることが大切です。
計画にはこれらを含むとよいです。
- 時間帯を決める
- 取り組む時間
- 休憩時間をどの程度とるか
- 優先順位を決める (宿題は最初にするなど)
宿題の延長で勉強していません。
朝起きてタブレットでアプリの問題(10分程度)をやっています。
勉強時間に比例して、習得が進むとは限りません。
宿題は夕食のまえに終わらせるようにしています。
4. ごほうびを決める
わかりやすいモチベーションアップの方法です。
宿題がおわったらテレビを見ていいとか、わかりやすいものがいいです。
ポイント制にして、ポイントがたまったらごほうびというのもありです。
うちはごほうびは特に決めていません。
5. ストレス対処
子どもだってストレスを感じています。
ストレスを解消するための時間を設けることです。
子どもの話を聞きましょう。聞いてもらうだけでも子どもは安心します。
私の場合、聞いて!といっても、聞けなかったり、スマホさわりながらの生返事をしてしまうことがよくあります。
子どもの顔をみて、聞いてるよ!の姿勢をつくります。
6. 成績より行動にフォーカスする
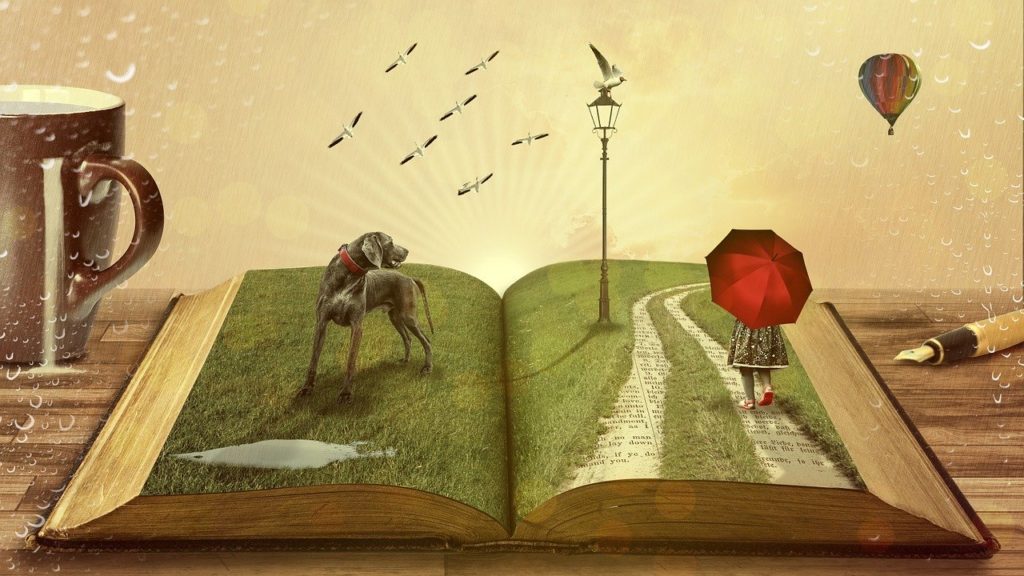
達成感はやる気のブースターです。
結果ではなく、ちょっとしたことでもやり遂げたらほめましょう。
「達成感 ⇒ 楽しい」を経験させることです。
私はあまりこれができていません。
私だけでなく主人やおばあちゃんにも報告して、ほめてくれる人数をふやしたりしました。
7. 小さな目標を立てる
ちょっとがんばれば達成できる目標を立てることです。
何をやれば達成できるか方向性が分かるからです。
こんな小さなことでOKです。
- 読書なら1章だけ
- 20分ノートを見直す
- 練習問題を5問やる
休校期間中に宿題がたくさんでました。
毎日これだけやるという計画を立ててもうまくいきません。
例えば毎日3ページとか決めたら、3ページ以上やらないことです。
次の日、きのう3ページ以上やったから今日はやらないという、さぼりのもとを断つのです。
8. 別のやり方を試す
解決方法はひとつではありません。
みんなが同じ解決方法で、うまくいくわけありません。
例えば、小さな目標を決めてもそれがうまくいかなかったらやめることです。
他の方法を試してみることです。
やめるのではなく、やり方を変えるのです。
夏休みのことです。午前中に宿題をやろうと決めたが、やりません。夜になってもやりません。
私がリビングでパソコンをやり始めたら、子どもたちは宿題をやり始めました。
次の日から、午前中にパソコンをさわりだしたら、いっしょの机で宿題をするようになりました。
なにがきっかけになるかわかりません。
9. 休憩時間をつくる
低学年の子どもだと、机に長時間向かわせること自体難しいです。
集中力の問題です。
勉強時間をできる範囲でぶつ切りにし、休憩をいれることです。
- 休憩時間を知らせるタイマーをセットする
- 30分勉強したら休憩
- 休憩は5~10分程度
個人差と本人の気分次第なので難しいところです。
小1の息子はアプリで漢字の問題を1時間くらいやっていました。
集中していたので、そっとしておきました。
10. 体を動かす
勉強のまえに、体を動かすことです。
血液が脳みそに流れるので、イライラや疲労回復に効果ありです。
仕事のまえにジムにいったり、筋トレしたりする方もいますね。
11. 第三者のヘルプ
子どもがいっぱいいっぱいになってしまわないよう、子どもの気持ちに耳を傾けることや、ときには先生に相談することも必要です。
近くにいる親だからこそ、見えないことがあります。
どんな問題にも立ち向かえる自信を育てていくサポーターは、親だけではありません。
親の背中をみて子どもは育つ
- 子どもをやる気にさせるには親の言動がカギ
- 原因を探り、親もいっしょに考える
- 小さい達成感⇒楽しいを経験させる
親の背中をみて子どもは育ちます。
親が読書好きなら、子どもも自然と読書する習慣ができます。
そして、子どもに親の夢をたくしてはいけません。
子どもは子どもの人生です。
期待をしすぎてもいけません。
「あんたのためを思っていっているのよ!」もダメですね。
子育てに正解はありません。親も一緒に成長していくのです。